リフォームで得する!住宅ローン控除を最大限活用する方法
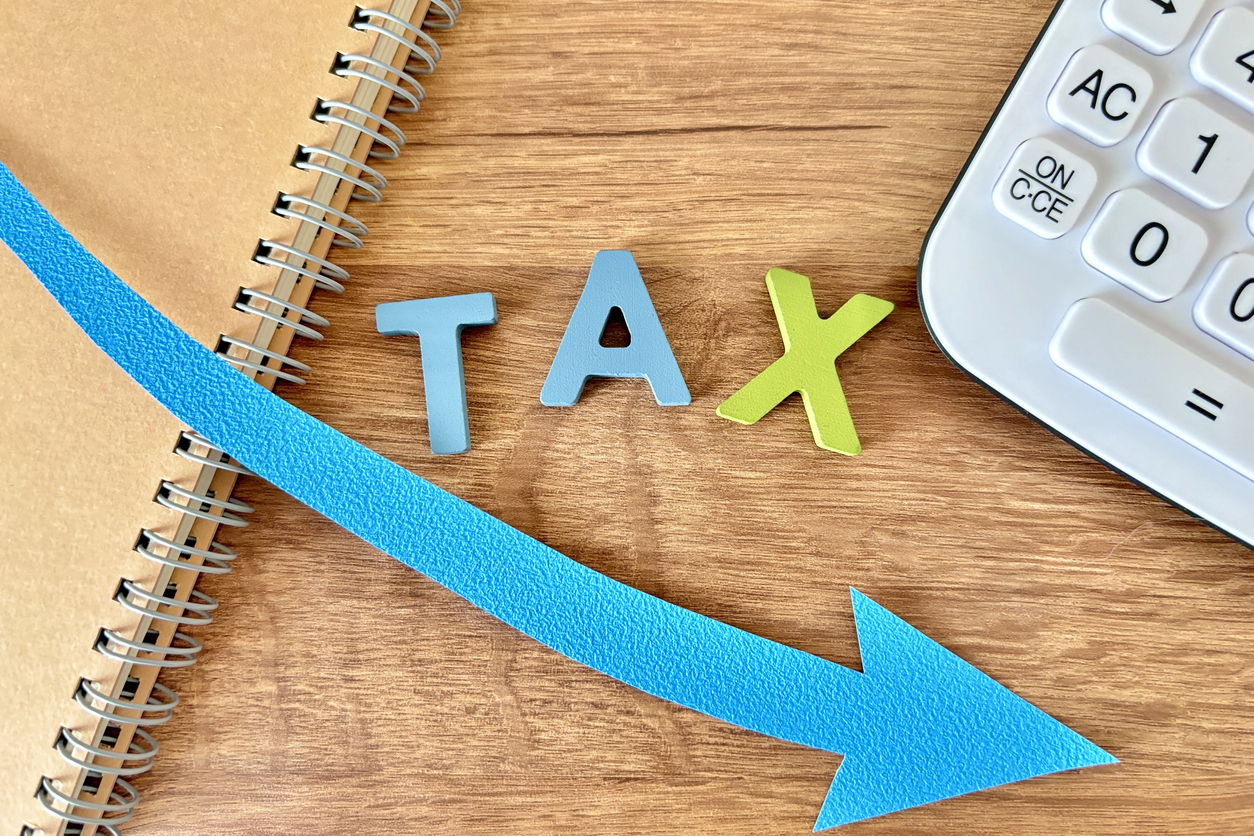
ローンを利用して住宅を購入した際に使うイメージの強い「住宅ローン控除」ですが、実は一定の要件を満たすリフォームでも利用できることをご存じでしょうか。リフォームローンを活用して大規模なリフォームを行う場合、住宅ローン控除を申請することで、経済的な負担を抑えられます。
この記事では、住宅ローン控除の対象となるリフォームの種類や要件、申請手続きなどの基本情報を網羅的に解説します。リフォームで使える「リフォーム促進税制」についても併せて解説するので、近いうちに自宅のリフォームを予定されている方は参考にしてください。
住宅ローン控除の基本
最初に住宅ローン控除がどのような制度なのか、基本を押さえておきましょう。住宅ローン控除とは、返済期間が10年以上のローンを利用して、住宅を取得したり一定の要件を満たす自宅のリフォームを行ったりした場合に、10年間もしくは13年間、所得税額の控除を受けられる制度です。所得税から控除しきれなかった分に関しては、翌年の住民税から控除される仕組みになっています。
次の表は、メニューや住宅種別ごとの控除額などをまとめたものです。
| 住宅種別 | 借入限度額(※) | 控除期間 | 最大控除額 (※) |
|---|---|---|---|---|
新築住宅等 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅 | 4,500万円 (5,000万円) | 13年間 | 409.5万円 (455万円) |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 (4,500万円) | 318.5万円 (409.5万円) | ||
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 (4,000万円) | 273万円 (364万円) | ||
中古住宅 | 省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 | 140万円 | ||
リフォーム | ― | 2,000万円 | 140万円 | |
※令和7年度税制改正後の内容 ※控除率はすべて共通で0.7% ※借入限度額および最大控除額のカッコ内は、子育て世帯・若者夫婦世帯における金額 ※2025年4月の法改正で、新築住宅は省エネ基準適合が義務化 | ||||
住宅ローンの控除対象となるリフォームの種類と要件
上で紹介したように、10年以上のローンを利用した自宅のリフォームでも、住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。控除対象となるリフォームの種類と主な要件を見ていきましょう。
控除対象となるリフォームの種類
住宅ローン控除となるのは、次に挙げる第1号工事〜第6号工事に該当するリフォームです。
リフォームの種類 | リフォームの内容 |
|---|---|
第1号工事 (増改築等) | 増築、改築、建築基準法における「大規模の修繕」もしくは「大規模の模様替え」 |
第2号工事 (増改築等) | マンションなどの区分所有部分において実施する、一定の修繕や模様替え |
第3号工事 (増改築等) | 居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床または 壁のすべてについて実施する、修繕や模様替え |
第4号工事 (耐震) | 耐震基準に適合させるために行う修繕や模様替え |
第5号工事 (バリアフリー) | お年寄りなどが自立した日常生活を営めるようにすることを目的とし、 一定の基準を満たす①〜⑧の修繕や模様替え ①通路または出入口の拡幅 ②階段の勾配緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差解消 ⑦出入口のドアの改良 ⑧床材の取り替え |
第6号工事 (省エネ) | すべての居室のすべての窓に対して行う断熱改修工事、 それと併せて実施する床・壁・天井などの断熱性を高める工事 ※リフォームにより、住宅全体の断熱等級が以前より1段階以上 アップすると認められることが必要 |
(出典)一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「【住宅ローン減税】 対象リフォーム」
控除を受けるための主な要件
自宅のリフォームで住宅ローン控除の適用を受けるには、工事内容が前述の第1号〜第6号工事に該当すること以外にも、いくつかの要件があります。
【住宅ローン控除を受けるための主な要件】
自ら購入し、居住する自宅に対するリフォームであること
住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に住み始めること
リフォーム後の居住部分の床面積が50m2以上であること
控除を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下であること
控除対象工事にかかる費用から、補助金などの金額を差し引いた残額が100万円を超えていること
併用住宅の場合、居住部分のリフォームにかかる工事費が全体工事費の1/2以上であること
これらの要件をすべて満たす場合のみ、住宅ローン控除が適用されます。
リフォームにおける住宅ローン控除の申請手続きと必要書類

すべての要件に当てはまり、実際に住宅ローン控除を申請する場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは、リフォームにおける住宅ローン控除の申請手続きの流れと、申請時の必要書類について詳しく解説します。
申請手続きの流れ
住宅ローン控除を活用する場合、工事翌年の確定申告で申請しなければなりません。具体的には、次の4ステップで手続きを進めます。
【住宅ローン控除の手続きの流れ】
①必要書類の準備
②必要書類の記入
③確定申告の実施(工事翌年の2月16日〜3月15日※土日と重なる場合は日付が変わる)
④還付金の受け取り
なお、会社員の場合、2年目以降は年末調整で手続きが完了するため、確定申告は初年度のみとなります。
リフォームにおける住宅ローン控除の必要書類
リフォームで住宅ローン控除の適用を受けるには、次の必要書類を準備したうえで確定申告を行う必要があります。上記のように確定申告は期間が決められているため、準備できるものから早めにそろえておくとよいでしょう。
・リフォームの住宅ローン控除を受けるための必要書類
書類 | 入手先 |
|---|---|
①確定申告書 | 税務署、国税庁ホームページ |
②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署、国税庁ホームページ |
③リフォームローンの年末残高等証明書 | ローンを組んでいる金融機関 (年1回郵送またはWEBでお知らせ) |
④リフォーム完了後の家屋の登記事項証明書 | 法務局 |
⑤工事請負契約書の写し | 施工したリフォーム会社 |
⑥(補助金の交付を受けた場合) 補助金決定通知書など | 交付元の自治体窓口 |
⑦増改築等工事証明書 | 指定確認検査機関など |
⑧(会社員の場合)源泉徴収票 | 勤務先 |
リフォームで使えるもう1つの減税制度「リフォーム促進税制」とは?

リフォームでは、住宅ローン控除のほかに「リフォーム促進税制」を活用できる可能性があります。リフォーム促進税制とはどのような制度で、住宅ローン控除と何が違うのか紹介しましょう。
リフォーム促進税制の概要
リフォーム促進税制とは、一定の要件を満たすリフォームを行った場合、工事にかかった費用に応じた金額を、工事が完了した年の所得税から控除できる制度です。同制度の対象となるリフォームの種類と最大控除額を表で確認しましょう。
リフォームの種類 | 最大控除額 |
|---|---|
耐震リフォーム | 62.5万円 |
バリアフリーリフォーム | 60万円 |
省エネリフォーム | 62.5万円/67.5万円※ ※太陽光発電設備設置工事を併せて行う場合 |
同居対応リフォーム | 62.5万円 |
長期優良住宅化リフォーム | 62.5万円〜80万円※ ※耐震+省エネ+耐久性向上+太陽光発電設備設置工事を行う場合 |
子育て対応リフォーム (2025年12月31日まで) | 62.5万円 |
(出典)一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの支援制度」
住宅ローン控除との違い
住宅ローン控除と共通している部分もあるリフォーム促進税制ですが、3つの点で大きく異なっています。
【リフォーム促進税制が住宅ローン控除と異なる3つのポイント】
①控除期間が工事を完了した1年のみであること
②ローンの利用有無にかかわらず使えること
③工事内容によって最大控除額が変わること
特にポイントとなるのが②です。住宅ローン控除は、返済期間10年以上のローンを借り入れていないと利用できないのに対し、リフォーム促進税制は現金払いでも適用されます。リフォーム促進税制の控除期間は1年のみですが、幅広く適用を受けられる制度といえるでしょう。
リフォーム促進税制の申告手続き
リフォーム促進税制も住宅ローン控除と同様、工事翌年の確定申告で申請する必要があります。リフォームの種類ごとに必要書類をまとめると次のとおりです。
リフォームの種類 | 必要書類 |
|---|---|
耐震リフォーム | ①確定申告書 ②住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 ③登記事項証明書 ④増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 |
バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 同居対応リフォーム 子育て対応リフォーム | ①確定申告書 ②住宅特定改修特別税額控除の計算明細書 ③登記事項証明書 ④増改築等工事証明書 ⑤(補助金の交付を受けた場合) 補助金決定通知書など |
長期優良住宅化リフォーム | ①確定申告書 ②住宅特定改修特別税額控除の計算明細書 ③登記事項証明書 ④増改築等工事証明書 ⑤長期優良住宅の認定通知書の写し ⑥(補助金の交付を受けた場合) 補助金決定通知書など |
(出典)国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」
リフォームで住宅ローン控除を活用するときの注意点

リフォームで住宅ローン控除を活用する際に気をつけたいのが、住宅ローン控除とリフォーム促進税制は基本的に併用できない点です。耐震リフォームのみ一部併用ができるものの、ほかのリフォームメニューに関しては、併用が認められていません。基本的に、返済期間10年以上のローンを利用している場合は「住宅ローン控除」、それ以外の場合は「リフォーム促進税制」と考えればよいでしょう。
なお、一定のリフォームで利用できる固定資産税の減税制度とは併用が可能です。
まとめ
住宅購入時に使うものというイメージの強い住宅ローン控除ですが、リフォームでも最大140万円の所得税控除が受けられる可能性があります。返済期間10年以上のローンを組んでいれば、比較的幅広い工事が対象となるため、今後自宅のリフォームをする際は活用を検討するとよいでしょう。
また、住宅ローン控除が利用できない場合でも、リフォーム促進税制は適用対象となるケースが少なくありません。これら2つの制度を最大限活用して、お得に自宅をリフォームしましょう。


.jpg)