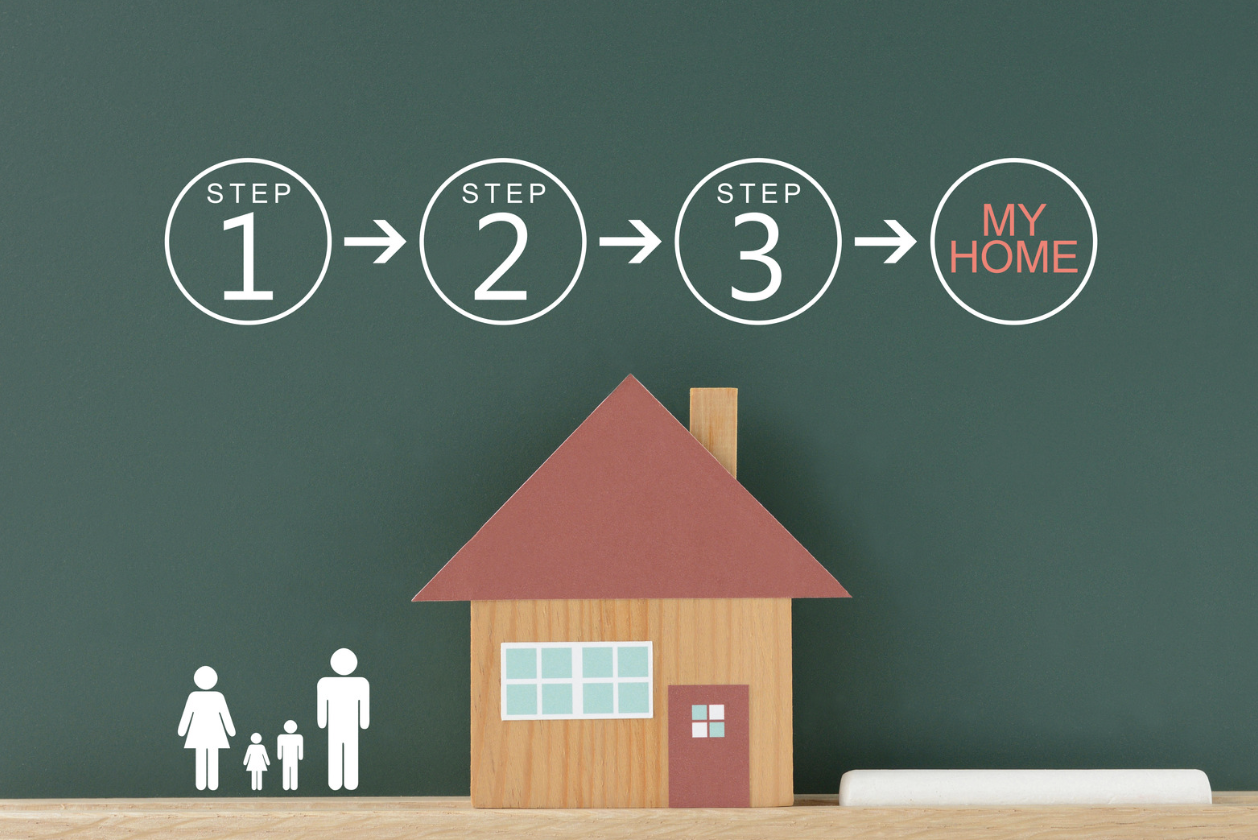住宅ローンの変動金利のリスク管理
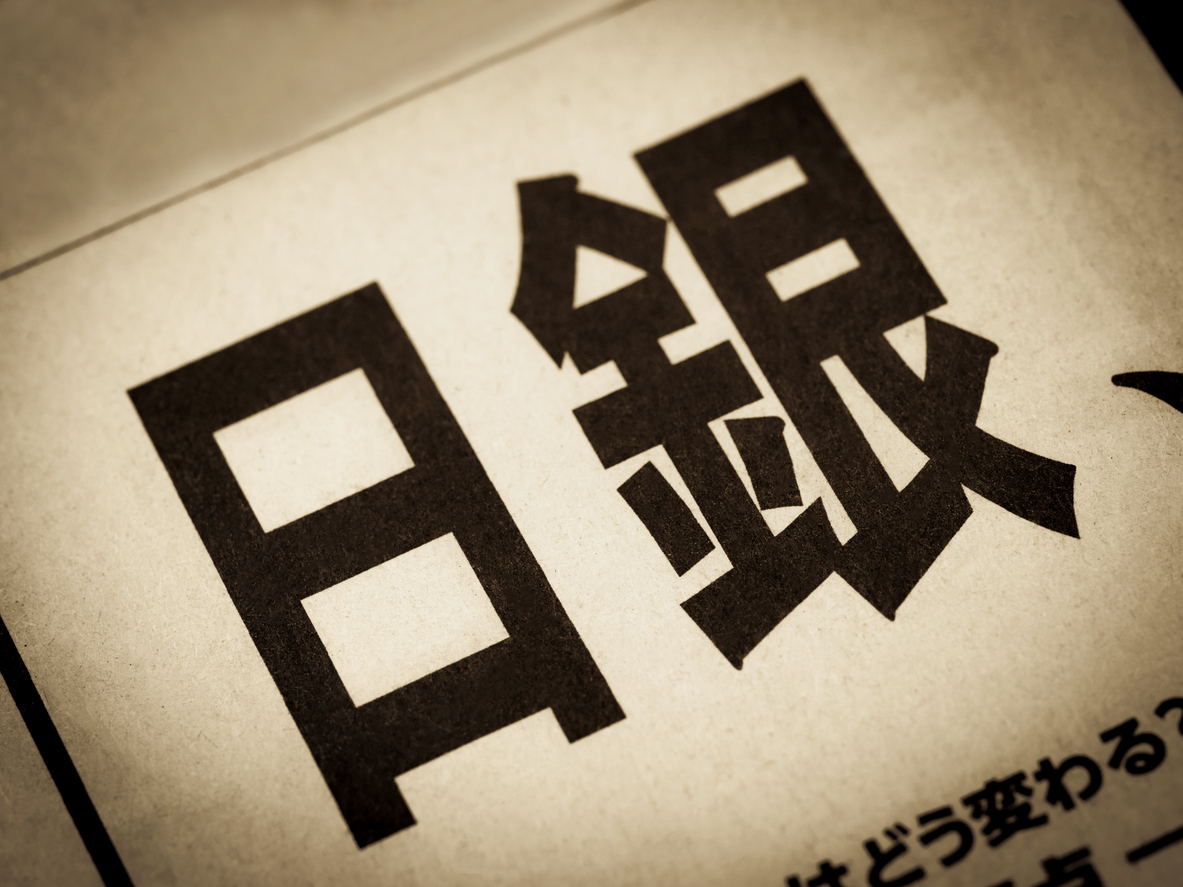
日銀が政策金利を引き上げることを決めました。
これによって多くの場所で様々な懸念があふれ出しているのですが、これは住宅ローンも例外ではありません。というのも、住宅ローンの金利も上がることを意味するからです。宅産業の関係者の全部が混乱していると言っても過言ではないでしょう。
では、この住宅ローン金利の引き上げによる混乱は住宅ローン利用者にどのように関連するのでしょうか。
そこで、ここでは住宅ローンの金利について取り上げ、特に変動金利とリスク管理について解説します。
住宅ローンの金利について

住宅ローン金利の引き上げと利用者の関連性を確認するためには、住宅ローン金利について知っておかなければいけません。
そこで、ここでは住宅ローン金利について解説します。
金利とは
まずは住宅ローンの金利について解説します。
さて、住宅ローンは銀行から資金を借り入れることです。銀行は利子を付けて貸してくれ、その利子を収益としています。
そして、その利子をどれくらい発生するかが金利なのです。
金利が高ければ利子が増えるので銀行に入る資金が増え、金利が下がれば銀行に入る資金は減ります。
つまり、金利が高ければ返済額が増え、低ければ返済額が減るのです。
住宅ローンの金利の種類
銀行などの金融機関に行くと、住宅ローンのパンフレットやポスターが貼ってあります。そこには金利についての記載があります。「固定金利〇〇パーセント・変動金利××パーセント」と大きく書いてあるのに気が付く人も多いことでしょう。
さて、この「金利」についている「固定」及び「変動」は金利の種類を表します。固定金利は「金利が
変わらない」ということを、変動金利は「金利が変動する」ことを意味します。
つまり、固定金利であれば返済額が変わらず、変動金利は返済額が変わるのです。
ちなみに、住宅ローンには一定期間を固定金利、その後を変動金利にしているケースも見られます。一定期間は同じ返済額、その後は返済額が変動する…という意味なのです。
金利はどの部分に掛かるか
ここで、金利はどの部分に掛かるかについて取り上げましょう。
住宅ローンは非常に多額の資金を融資してもらいます。例えば、5,000 万円、6,000 万円、といった金額です。しかし、全額を融資してもらうとは限りません。一般にはある程度の自己資金を用意し、その不足分を借ります。例えば、5,000 万円の物件を購入する場合には 500 万円を自己資金、4,500 万円を融資で補う、という恰好です。そして、金利は融資の部分、つまり 4,500 万円の部分に掛かります。
複利計算の考え方
では、金利はどのように掛かるのでしょうか。利子はどのように計算されるのでしょうか。
これは「複利計算」で発生します。
金利には「単利」と「複利」があり、住宅ローンは複利で発生するのです。
では、単利と複利はどのように違うのでしょうか。
単利について
単利計算は借入額の元金のパーセンテージで決まります。
例えば、金利が 1 パーセントで 1000 万円を借りる場合、毎年 10 万円ずつ発生するのです。
この条件で 1~10 年で借りるとすれば、1 年ごとの返済額以下のような計算となります。
1 年:1,010 万円:1,000+1,000×0.01
2 年:1,020 万円:1,000+1,000×0.01×2
3 年:1,030 万円:1,000+1,000×0.01×3
4 年:1,040 万円:1,000+1,000×0.01×4
5 年:1,050 万円:1,000+1,000×0.01×5
6 年:1,060 万円:1,000+1,000×0.01×6
7 年:1,070 万円:1,000+1,000×0.01×7
8 年:1,080 万円:1,000+1,000×0.01×8
9 年:1,090 万円:1,000+1,000×0.01×9
10 年:1,100 万円:1,000+1,000×0.01×10
このように計算は単純です。
ただし、この金利は融資を受ける場合には適用されません。適用されるのは預金の 1 部です。
複利について
複利計算は元金に利子を含めた金額のパーセンテージで決まります。
例えば、金利が 1 パーセントで 1000 万円を借りる場合、10 万円を起点として、返済額が増えて行くのです。
前述同様に 1~10 年で借りるとすれば、返済額は次のように変動します。
1 年:1,010 万円:1,000+1,000×0.01
2 年:1,020.1 万円:1,010+1,010×0.01
3 年:1,030.3 万円:1,020.1+ 1,021.1×0.01
4 年:1,040.6 万円:1,030.3+1,030.3×0.01
5 年:1051.0 万円:1,040.6+1,040.6×0.01
6 年:1061.5 万円:1,051.0+1051.0×0.01
7 年:1,072.1 万円:1,061.5+1,061.5×0.01
8 年:1,082.9 万円:1,072.1+1,072.1×0.01
9 年:1,093.7 万円:1,082.9+1,082.9×0.01
10 年:1,104.6 万円:1,093.7+1,093.7×0.01
このように、単利で借りるよりも返済額が増えます。つまり、銀行に支払う費用が増えるのです。
複利で金利が上がるとどうなるか
ところで、冒頭に挙げた通り、政策金利が上がり、住宅ローン金利も上がります。
では、複利計算で金利が上がると、返済額はどのように変わるのでしょうか。前述の条件で金利を 1.2パーセントで計算してみましょう。
1 年:1,012 万円:1,000+1,000×0.012
2 年:1,022.1 万円:1,012+1,012×0.012
3 年:1,032.3 万円:1,022.1+ 1,022.1×0.012
4 年:1,042.7 万円:1,032.3+1,032.3×0.012
5 年:1053.1 万円:1,042.7+1,042.7×0.012
6 年:1063.7 万円:1,053.1+1053.1×0.012
7 年:1,074.3 万円:1,063.7+1,063.7×0.012
8 年:1,082.9 万円:1,074.3+1,074.3×0.012
9 年:1,095.9 万円:1,082.9+1,082.9×0.012
10 年:1,106.8 万円:1,095.9+1,095.9×0.012
このように、金利が少し上がっただけで利子が上がってしまいます。
ちなみに、住宅ローンには 35 年のものもありますが、この調子で利子が上がったら確かに大変です。
変動金利リスクの回避方法

ここでは、変動リスクの回避方法について取り上げます。
なお、当然ではありますが、これらの手段は複数を組み合わせるとより効果的です。
確かに、1 つの案でも行えば効果は上がるでしょうが、政策金利の上昇に追いつけるとは限りません。
可能なだけの手段を取ることをおすすめします。
自己資金を多くする
前述のように、利子は借入分に発生します。
そのため、自己資金を増やして借入金を減らせば利子を減らすことが可能です。
例えば 5,000 万円の物件を 500 万円の自己資金で借りる場合と 800 万円の自己資金で借りる場合は 300万円の開きがあります。つまり、300 万円に発生する利子を抑えることが可能なのです。
返済のタイミングを見定める
返済のタイミングで発生する利子を抑えることが可能な場合があります。
これはボーナス払いを応用してのこと。ボーナス払いを初回に持ってくれば、それだけ自己資金の比率が上がり、借入分を減らすことが可能なのです。
今では物価高騰を受けて賃金が上がっている業界が少なくありません。そのような業界・企業に勤務するならば、高額のボーナスが期待できるでしょう。このタイミングに合わせてローンをスタートさせてはどうでしょうか。
繰り上げ返済をする
繰り上げ返済も利子を抑えるのに有効です。
というのも、繰り上げ返済は元金の返済に充てられるからです。利子は借り入れている部分に発生するので、元金を減らすことができれば減らせます。
ちなみに、繰り上げ返済の方法によって手数料の有無があります。ネットバンキングならば無料の場合もあるので、上手に活用したいものです。
金利は値切れる場合がある
金利は銀行のパンフレットなどに書いている通りなのですが、金利は値切れる場合があります。
例えば、1.0 パーセントを 0.7 パーセントに値引きする…といったことが可能なのです。
当然ながら、これは銀行の営業マンとの交渉によって成立するもの。一般的には語られません。
ただ、上手く行けば 100 万円を超えるメリットも夢ではありません。交渉してみると良いでしょう。
ちなみに、このような交渉は決算前などに持って行けば通りやすくなるようです。銀行マンも業績が欲しがるのが決算前です。
もしかすると、銀行マン弱みを突くようにも思えるかも知れませんが、それで多額の資金が変わります。心を鬼にする時なのかも知れません。
まとめ
住宅ローンの変動リスク管理について取り上げました。
少し面倒な計算にはなりましたが、金利の発生についてもイメージできたことと思います。また、上手な利用方法も把握できたのではないでしょうか。
経済状況は混迷を続けていますので、今後の金利はどのようになるか分かりません。また、税金などの問題も他で発生することもあり得ます。
そのような場合には、やはり自衛が一番です。可能な限りの情報を集め、経済的な補強を続けましょう。
関連記事
人気の事例こだわりタグ: