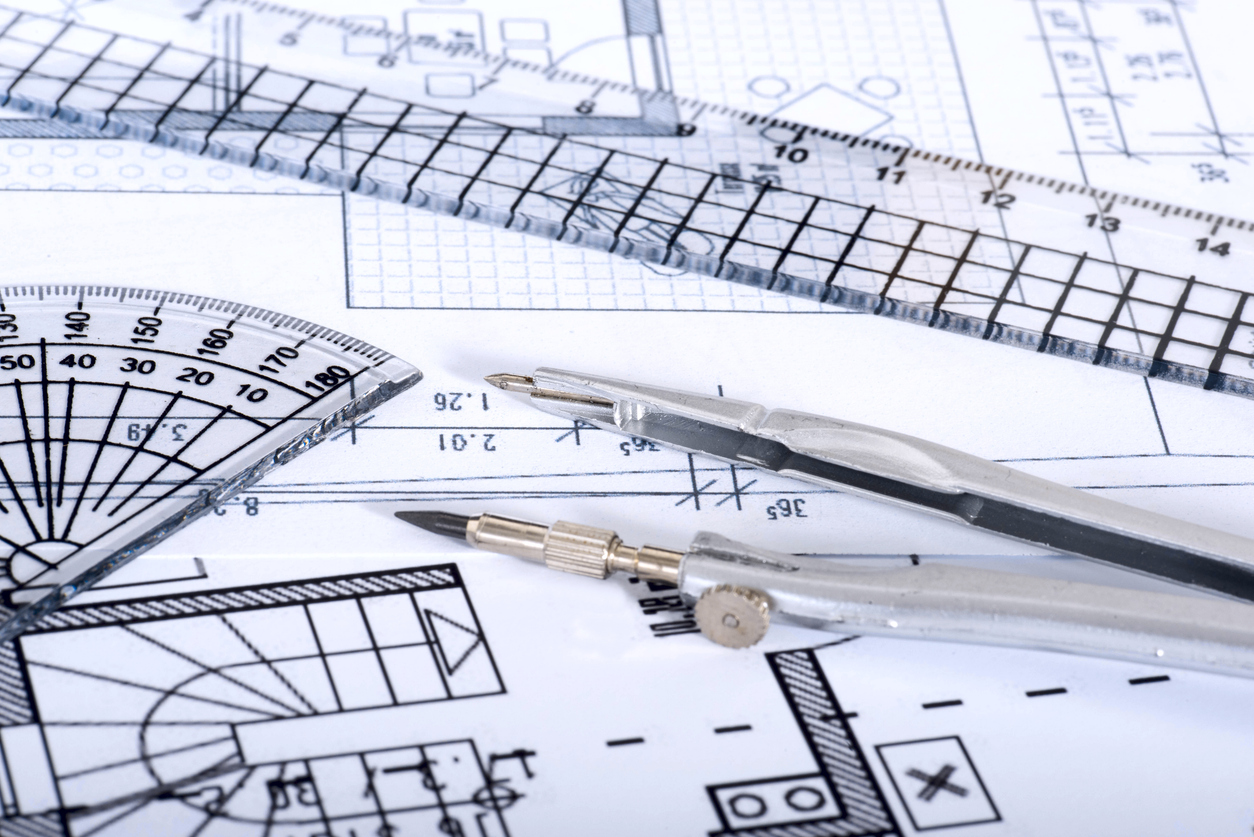建築基準法とは?安全・快適な住 まいづくりのために知っておくべき基本
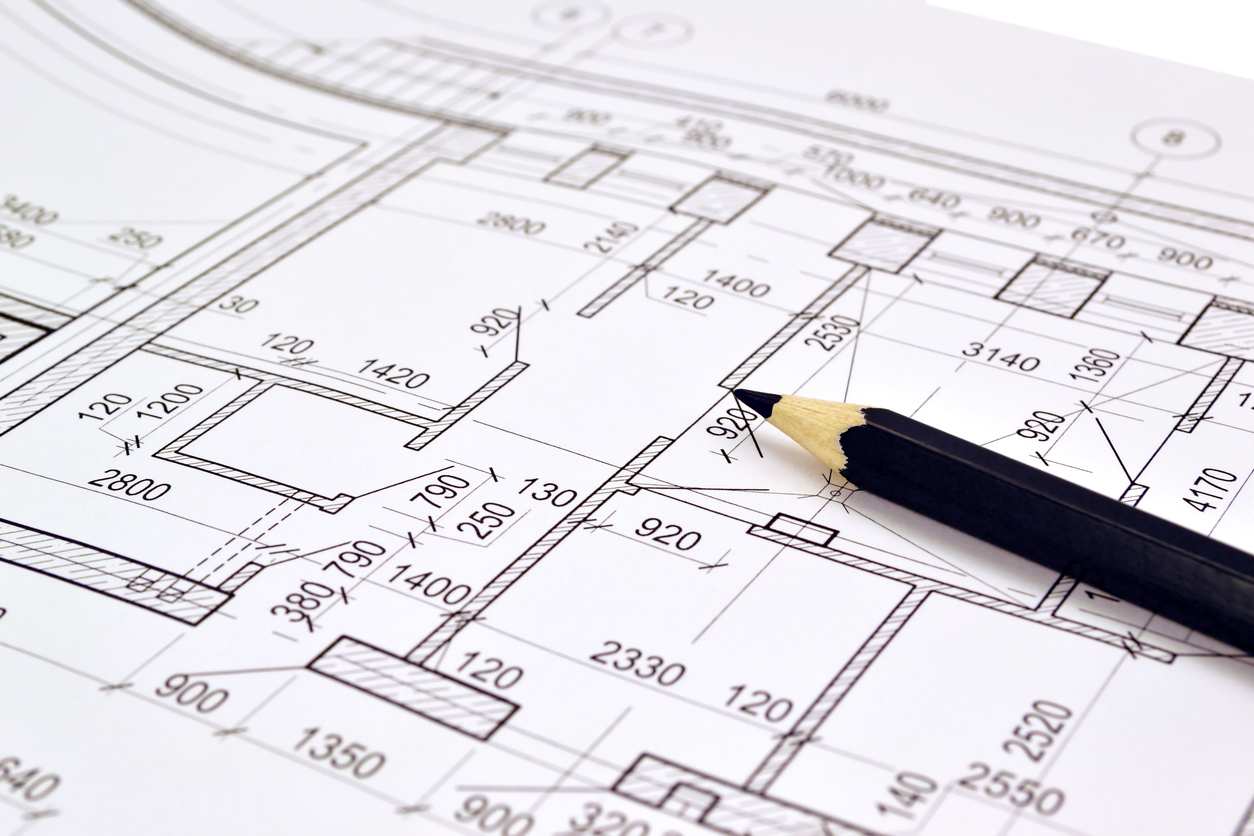
建築におけるさまざまなルールを定めた建築基準法は、住まいづくりにおいてもすべての基本となる法律です。住宅の新築時やリフォーム時には、建築基準法の規定に沿って、安全かつ快適な建物環境を整備することが求められます。
この記事では、住まいづくりに関わるポイントを中心に、建築基準法の概要や規定について詳しく解説。2025年4月施行の改正の内容についても紹介します。
建築基準法とは?目的、規定の種類をチェック
まず、建築基準法とはどのような法律で、どのようなことを規定しているのか確認しておきましょう。
建築基準法の目的
建築基準法第1条において、制定の目的が述べられています。
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(引用)e-Gov法定検索「建築基準法」
建築基準法とは、簡単にいえば、建物の建築や利用にあたっての最低限のルールを定めることで、国民の命や暮らし、財産などを守るための法律です。1950年に制定されて以降、社会情勢の変化や大規模災害の発生などに応じて、都度改められてきました。
単体規定と集団規定
建築基準法の規定は、大きく「単体規定」と「集団規定」に分けることができます。
規定の内容 | 適用地域 | |
|---|---|---|
単体規定 | 個別の建物の構造や設備の規定 | 全国 |
集団規定 | 建物と周辺環境の関わりの規定 | 都市計画区域・準都市計画区域内 |
単体規定に分類されるのは、防火性能、耐震基準、必要施設に関するものなど、個別の建物を建築する際に守るべき内容です。一方、集団規定に分類されるのは、建ぺい率・容積率、道路と敷地の関係、防火地域など、周辺環境の整備や保全のために必要な規定となっています。
建築確認と完了検査
計画されている建物が、建築基準法の規定に沿っているかどうかをチェックするため、新築工事着工前に「建築確認」を申請することが義務付けられています。建築確認をクリアして「確認済証」の交付を受けて初めて、新築工事を着工することが可能です。
また、建築確認申請の内容どおりに工事が行われたかを確認するため、工事完了後には「完了検査」を受ける必要があります。完了検査を無事通過すると「検査済証」が交付されます。
この手続きは住宅においても例外ではなく、住宅新築時や「大規模の修繕・模様替え」に該当するリフォームでも必要です。
建築基準法の主要な規定

建築基準法には、どのような規定があるのでしょうか。住宅の建築に関わるものをピックアップして紹介します。
主要な単体規定
単体規定で、住宅の建築に大きく関わるのが、耐震基準と居室に関する規制の2つです。
①耐震基準
耐震基準は、大地震発生時、建物にいる人々の命や暮らしを守るために定められる、建物構造に関する最低限の基準です。
震災で大きな被害が発生するたびに内容が見直されており、1981年6月の改正以降の耐震基準を「新耐震基準」、それ以前の基準を「旧耐震基準」とするのが一般的です。新耐震基準では、震度6強程度の大地震でも倒壊・崩壊しない程度の強度が求められます。
なお、現行基準は「2000年基準」と呼ばれるもので、1995年の阪神・淡路大震災を受けて見直された基準です。木造住宅に関する規定が大きく見直されており、2000年基準を満たすかどうかが、戸建て住宅の耐震性における重要な判断基準となっています。
②居室に関する規制
単体規定でもう一つ確認しておきたいのが、居室に関する2つの規制です。建築基準法では、健康的かつ安全な暮らしを守るため、居室の採光と換気について、以下のように規定しています。
採光に関する規定 | 採光できる窓などの開口部を、居室の床面積の1/7以上設けること |
換気に関する規定 | 直接外気につながる開口部を、居室の床面積の1/20以上設けること |
この規定により、窓がなかったり小さかったりして、採光面積が不足している部屋は居室として扱えません。例えば、「サービスルーム」や「納戸」などと呼ばれる部屋が該当します。
主要な集団規定
集団規定についても、住まいに関わるものを中心にピックアップして紹介します。
①用途地域
用途地域とは、建てられる建物の用途や面積などを規定した地域区分のことです。市街地を13種類の用途地域に分類し、良好な住環境や計画的な市街地形成を促すことを目的としています。13種類の用途地域の内容は、この後の章で詳しく解説します。
②道路と敷地の関係
建物を建てるための敷地は、原則幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない、とされています。この規定は一般的に「接道義務」と呼ばれます。道路から奥まったところにある旗竿地でも、通路の接道部分を2m以上確保する必要があるため注意しましょう。
接道義務が定められているのは、災害時の避難経路を確保するとともに、緊急車両が建物の近くまで入って来られるようにするためです。
③高さ制限、建ぺい率・容積率
建築基準法では、建物の高さを制限するための規定が設けられています。例えば、低層住宅地の良好な環境を保全するための「絶対高さ制限」、道路や近隣建物などの採光・通風の確保、圧迫感の緩和を目的とした「斜線制限」などです。制限の内容は、後の章で詳しく解説します。
ここでは、住宅の建築に大きく影響する規定として、建ぺい率と容積率を紹介しましょう。
建ぺい率 | 敷地面積に占める建築面積(建物を上空から見たときの面積)の割合 |
容積率 | 敷地面積に占める建物の延床面積(すべての階の床面積を合計した面積)の割合 |
建ぺい率・容積率は用途地域ごとに定められ、規定を超える規模の建物は原則建てられません。つまり、建物は敷地に対して一定の余裕を持って建てなければならず、敷地を目一杯使って家を建てることはできないのです。
用途地域
先ほど紹介したように、市街地として整備されている地域、あるいは今後整備される予定の地域(市街化区域・都市計画区域)では「用途地域」が定められています。用途地域は「住居系」「商業系」「工業系」の3種類に分けられ、さらに細かく全部で13種類の地域が設定されています。
住居系
用途地域の種類 | 概要 |
|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅を建てるための地域。 小規模な店舗や事務所の併用住宅、小中学校などが建築可能。 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅を建てるための地域。 150㎡までの一定の店舗などが建築可能。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅を建てるための地域。 病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建築可能。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅を建てるための地域。 1,500㎡までの一定の店舗やオフィスなどが建築可能。 |
第一種住居地域 | 居住環境を守るための地域。 3,000m2までの店舗、オフィス、ホテルなどが建築可能。 |
第二種住居地域 | 主に居住環境を守るための地域。 店舗、オフィス、ホテル、カラオケボックスなどが建築可能。 |
準住居地域 | 道路の沿道に指定され、自動車関連施設などの建築が可能。 |
田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。 住宅のほか、農産物直売所などが建築可能。 |
商業系
用途地域の種類 | 概要 |
|---|---|
近隣商業地域 | 周辺住民の日常的な買い物のための地域。 住宅、店舗、小規模工場が建築可能。 |
商業地域 | 商業施設が集まる地域。 住宅、小規模工場も建築可能。 |
工業系
用途地域の種類 | 概要 |
|---|---|
準工業地域 | 軽工業の工場、サービス施設などが立地する地域。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域。学校、病院、ホテルなどは建築不可。 |
工業専用地域 | 工場のみ建てることができる地域。 |
(出典)国土交通省「用途地域」
所有・購入する土地がどの用途地域に属していて、何を建てることができるのか確認しましょう。また、周辺にどのような建物が建つ可能性があるのかも、用途地域を見れば想定ができます。
建物の高さ制限
続いて、家づくりで関係してくる、建物の高さに関する制限の内容を紹介します。戸建て住宅を建築する際に影響してくるのは、主に絶対高さ制限と道路斜線制限です。
高さ制限の種類 | 概要 |
|---|---|
絶対高さ制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域で適用される、 日照や低層の住環境を守るための高さ制限。 高さ10mまたは12m以内で、都市計画において規定。 |
道路斜線制限 | 全地域で適用される、道路の日照や環境確保のための高さ制限。 |
隣地斜線制限 | 隣接する建物同士の日照や住環境を守るために設定される高さ制限。 低層住居専用地域以外で適用され、地面から20mを超える部分からが制限対象。 |
北側斜線制限 | 住宅地で、北側にある敷地の日照を確保する目的で設定される高さ制限。 |
建ぺい率や容積率だけでなく、上記の高さ制限によっても、規模の制約を受けるということを覚えておきましょう。
自宅の建築・リフォームにおける建築基準法違反のリスクと対策

自宅の建築・リフォームにおいて建築基準法違反があれば、罰則を受ける恐れがあります。
違反に該当するケースと罰則の内容、違反を防ぐための対策について見ていきましょう。
違反に該当するケースと罰則
自宅の建築・リフォームで、建築基準法違反に該当するのは次のようなケースです。
違反内容 | 罰則 |
|---|---|
建築確認申請を行わなかった | 1年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
建築確認申請の内容に虚偽があった | 1年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
建築確認申請の内容と異なる工事を勝手に行った | 行政からの措置命令・警告 (措置命令に違反した場合) 3年以下の懲役 または300万円以下の罰金 |
上記の罰則の対象は、基本的に設計者や施工者です。しかし、施主の故意による違反と認められた場合、施主に罰則が適用される可能性もあるので注意しましょう。
違反を防ぐために有効な対策
基本的に罰則を受けるのは設計者・施工者ですが、違法建築物となれば、施主にも大きな影響が及びます。例えば、住宅ローンが借りられない、違法状態が是正されるまで住めないといった事態が考えられるでしょう。
こうした違反を防ぐには、確認済証の交付を受けるだけでなく、完了検査を受けて、検査済証の交付もしっかりと受けることが大切です。建築基準法関連の手続きは施工会社が行いますが、施主も常に内容をチェックし、疑問を残さないようにしておきましょう。
【2025年4月施行】建築基準法改正のポイント

2025年4月に建築基準法が改正されました。住宅の新築やリフォームに関わる内容について、ポイントを解説します。
「4号特例」の縮小
従来、木造2階建て住宅などは「4号建築物」として、新築時の建築確認申請における構造関係書類の提出などが省略できました(4号特例)。しかし、今回の改正で木造2階建てや床面積200m2超の平屋に関しては、審査省略制度の対象外となっています。
木造2階建ての確認申請時にも、新たに構造関係や省エネ関連の図書を提出しなければならなくなり、構造計算が実質義務化されたのがポイントです。
また、これまで建築確認申請の対象外だった、木造2階建てにおける「大規模な修繕・模様替え」に該当するリフォームも申請が必要になりました。今後、スケルトンリフォームを行う場合には、建築確認申請が求められる可能性が高いので要注意です。
構造計算に関する規定の見直し
構造計算が必要な建物の範囲が広がったのに伴い、構造計算に関する規定が一部緩和されました。具体的には、高度な構造計算を行わず、二級建築士による簡易な構造計算(許容応力度計算)で良いとされる木造建物の範囲が、以下のとおり見直されています。
(旧)高さ13m以下かつ軒高9m以下
(新)階数3以下かつ高さ16m以下
これにより、3階建てや高天井で高さのある木造建築などで、構造計算を簡易化できるようになりました。
省エネ基準適合の義務化
今回の改正で、もう1つ大きなポイントとなるのが、すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化された点です。建築確認を申請すると、審査において省エネ基準への適合性がチェックされます。
省エネ基準は「一次エネルギー消費量基準」と「外皮基準」からなり、両方が一定の基準を満たしていないと、確認済証が交付されないことになります。
一次エネルギー 消費量基準 | 住宅におけるエネルギー消費量から太陽光発電などによる 創エネ量を差し引いた「一次エネルギー消費量」が基準値 以下になること。 |
外皮性能 | 外皮平均熱貫流率(UA値:室内と外気の熱の出入りのしやすさを表す指標)、 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値:日射による熱の室内への入りやすさを表す指標)が、 地域区分ごとの基準値以下になること。 |
建築基準法の規定をしっかり守って、安全・快適な住まいづくりを!
建築基準法は、私たちの生命や暮らしを守るために制定された法律です。規定には細かなものも多く、設計や間取りにこだわろうとすると厄介に感じる瞬間があるかもしれません。しかし、建築基準法は、過去の社会情勢や震災を教訓に改められてきた歴史があります。わずらわしいように見えても、建物の安全性や強度、周辺環境との調和などを考慮した、大切な規定ばかりです。
建築基準法の規定は必ず守り、自分や家族が安全で快適に暮らせる住まいづくりを実現しましょう。