建ぺい率って何?リフォーム・リノベーション計画に欠かせない基本知識
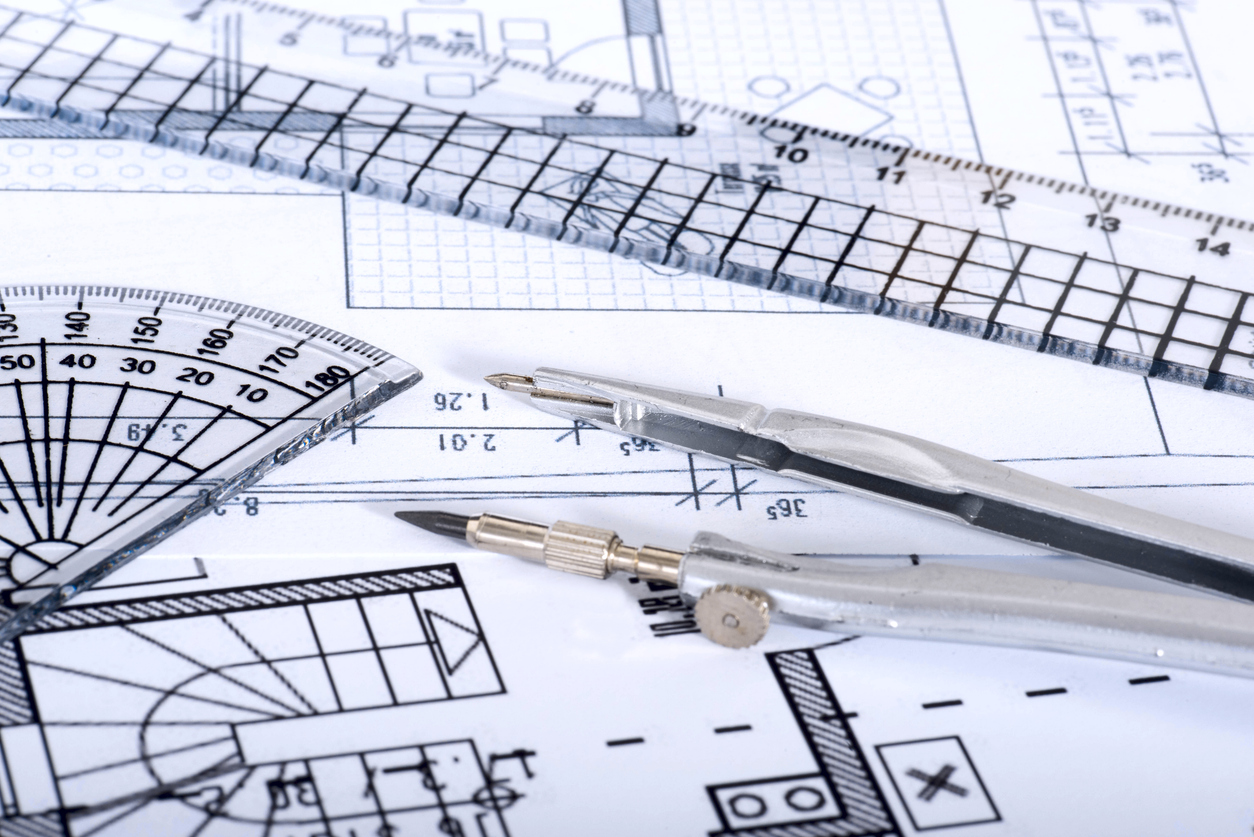
「リフォームやリノベーションを計画しているけど、『建ぺい率』って何のことだろう?」
「うちの家、建て増ししたいけど、建ぺい率って関係あるの?」
戸建ての増改築や大規模なリフォームを考える際、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。建ぺい率などの建築基準法のルールは、家づくりの自由度や可能性を左右する重要な要素です。
この記事では、リフォーム・リノベーションを成功させるために知っておきたい「建ぺい率」の基本知識について、容積率との違いも交えながら分かりやすく解説します。ご自身の住まいが、どのようなルールの上に成り立っているのかを理解し、理想のリフォーム計画を進めるための参考にしてください。
建ぺい率って何?容積率との違い

建ぺい率も容積率も、敷地に対して建てられる建物の大きさを制限する建築基準法上のルールです。どちらも土地の有効活用と、都市の環境維持のために設けられています。
建ぺい率は風通し・防災のための基準
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指します。簡単に言うと、「土地の広さに対して、建物を上から見たときにどれくらいの面積を建てていいか」というルールです。
例えば、敷地面積が100㎡で建ぺい率が50%の場合、建てられる建物の建築面積(1階部分の面積や、2階以上で1階より広い部分の面積)は最大で50㎡までとなります。
この建ぺい率が定められている主な目的は、良好な住環境の維持と防災です。建物同士の間に十分な空間を確保することで、日当たりや風通しを良くし、居住者の快適性を高めます。また、火災が発生した際に延焼を防いだり、避難経路を確保したりするなど、都市全体の安全性を高める役割も担っています。
容積率は人口コントロールのための基準
一方、容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(建物の各階の床面積の合計)の割合を指します。こちらは、「土地の広さに対して、建物のすべての階を合わせた床面積の合計がどれくらいまで建てていいか」というルールです。
例えば、敷地面積が100㎡で容積率が150%の場合、建てられる建物の延べ床面積は最大で150㎡までとなります。
容積率の主な目的は、都市計画における人口密度のコントロールです。
建物の延べ床面積を制限することで、特定の地域に人が集中しすぎるのを防ぎ、道路や公共施設(上下水道、学校など)の容量を適切に保ち、都市機能が麻痺しないように調整する役割があります。
建ぺい率・容積率の調べ方
ご自身の土地の建ぺい率と容積率は、以下の方法で調べることができます。
役所の建築関連部署(都市計画課、建築指導課など)で確認する
インターネットの都市計画情報サイトを利用する
不動産会社の重要事項説明書を確認する
建築士やリフォーム業者に相談する
これらの情報を正確に把握することで、基準法に則ったリフォーム・リノベーションを行えます。
建ぺい率はリフォーム・リノベーションにどんな影響があるの?

建ぺい率は、現在の住まいの改修において非常に重要な要素となります。特に、建物の規模や形に影響を与えるリフォーム・リノベーションを計画する際には、建ぺい率のルールが密接に関わってきます。
増築リフォームで確認申請が必要
現在の建物の面積を増やす「増築リフォーム」を行う場合、多くの場合で建築確認申請が必要になります。建築確認申請とは、計画している建物や増築部分が建築基準法などの法令に適合しているかを、行政や指定確認検査機関が審査する手続きのことです。
増築を行う際、増築後の建物の建築面積が、その土地に定められた建ぺい率の制限を超えてしまうと、原則としてその増築は認められません。
例えば、敷地面積100㎡で建ぺい率50%の土地に、現在建築面積40㎡の建物が建っているとします。この場合、あと10㎡までなら増築が可能ですが、それ以上増築しようとすると建ぺい率オーバーとなり、計画を見直す必要が出てきます。
したがって、増築を伴うリフォームを計画する際は、事前に建ぺい率を把握し、増築後の建築面積が基準内に収まるかを必ず確認する必要があります。
既存不適格建築物の大規模リフォームは確認申請時に是正を求められることも
古い建物の中には、建築された当時は適法であったものの、その後の法改正によって現行の建築基準法に合致しなくなってしまった「既存不適格建築物」が存在します。建ぺい率がオーバーしている建物も、この既存不適格建築物に含まれることがあります。
このような既存不適格建築物で、大規模なリフォームやリノベーションを行う場合、原則として現行の建築基準法に適合させる是正が求められることがあります。
具体的には、建ぺい率がオーバーしている既存不適格建築物を大規模にリフォームする際には、確認申請の際に「既存不適格状態のままでは許可できない」と判断され、減築を求められるなど、建ぺい率が現行の基準に収まるように是正が必要となる可能性があるということです。
ただし、既存不適格建築物については緩和措置が適用されるケースや、工事内容によっては是正が求められない場合もあります。この点は非常に複雑であるため、既存不適格の可能性がある場合は、必ず専門家である建築士やリフォーム業者、または自治体の建築指導課に事前に相談することが不可欠です。
建ぺい率の計算が必要なリフォームは?

「リフォームだから大丈夫」と思っていても、実は建ぺい率の計算に含まれてしまう工事もあります。うっかり基準を超えてしまわないよう、どのようなリフォームが建ぺい率に影響するかを確認しておきましょう。
建物の増築
建物の床面積が増えるような増築は、当然ながら建ぺい率の計算に含まれます。例えば、部屋を広げたり、新たにサンルームを設置したりする場合などが該当します。建築確認申請が必要となる規模の増築を行う際は、増築後の建築面積が建ぺい率の制限を超えないように注意が必要です。
屋根付きカーポートや物置の施工
屋根付きのカーポートや、基礎を打って地面に定着させるタイプの物置なども、建築基準法上は「建築物」とみなされ、建ぺい率の計算に含まれる場合があります。
特に、固定された柱と屋根がある構造物は注意が必要です。簡易的な自転車置き場や、移動可能な物置などは対象外となることが多いですが、判断が難しい場合は専門家への確認が必須です。フェンスや塀の設置は通常建ぺい率には影響しませんが、その規模や構造によっては確認が必要になるケースもゼロではありません。
建ぺい率の増減が伴うリフォーム・リノベーションでの注意点

建ぺい率が関わるリフォーム・リノベーションは、計画段階での確認が非常に重要です。後で「知らなかった」とならないように、以下の点に注意しましょう。
用途地域を確認する
建ぺい率の制限は、土地が指定されている「用途地域」によって異なります。用途地域は、市街地を計画的に利用するために定められた地域区分で、商業地域や住居地域など、全部で13種類あります。それぞれの用途地域には、建てられる建物の種類や建ぺい率、容積率、高さなどが細かく定められています。
リフォーム計画を立てる前に、ご自身の土地がどの用途地域に属しているか、そしてその地域で定められている建ぺい率が何%であるかを必ず確認してください。これにより、どの程度の増築が可能か、もしくは既存不適格建築物により減築が必要になるかの判断基準となります。
確認申請が必要な工事内容を確認する
建ぺい率に関わるリフォームだけでなく、その他の工事でも建築確認申請が必要になる場合があります。特に、以下のような工事は確認申請の対象となる可能性が高いです。
増築・改築
大規模の修繕・模様替え
建築物の用途変更
これらの工事を行う際は、建ぺい率だけでなく、他の建築基準法や関係法令にも適合しているかどうかの審査を受けなければなりません。
リフォーム業者と綿密に打ち合わせを行い、計画している工事内容が確認申請の対象となるか否かを事前に確認することがトラブルを避ける上で非常に重要です。
まとめ

建ぺい率は、敷地に対する建物の建築面積の割合を制限する建築基準法上のルールであり、日当たりや風通し、防災の観点から定められています。容積率と合わせて、土地の利用方法を規制する重要な指標です。
リフォーム・リノベーションにおいては、増築を行う際に建ぺい率の制限に抵触しないか、また、既存不適格建築物の場合は大規模な改修時に現行法への是正が求められる可能性があるなど、大きな影響を及ぼします。特に2025年4月の法改正により、確認申請が必要な工事の範囲が拡大されるため、これまで以上に事前の確認が不可欠です。
リフォーム計画を進める際は、ご自身の土地の用途地域と定められた建ぺい率を正確に把握し、計画する工事内容が建築確認申請の対象となるかを確認しましょう。これらの専門的な判断は、大和ハウスウッドリフォームのような経験豊富なプロに相談するのが最も確実です。安心して理想のリフォーム・リノベーションを実現するために、ぜひお気軽にお問い合わせください。


