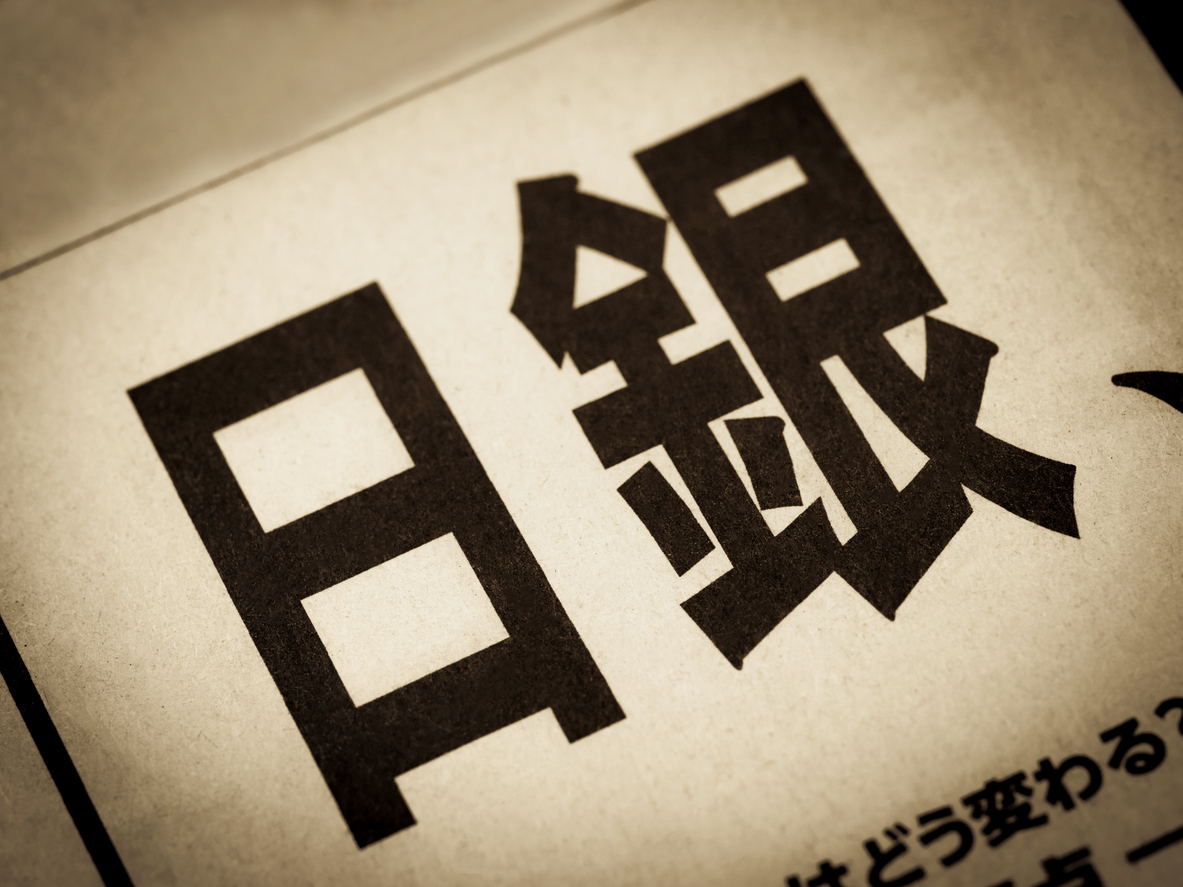土地売却にかかる3種類の税金の計算方法と支払い時期|税額のシミュレーションも!

所有する土地を売却すればまとまった資金を得られますが、一方で、どれくらい税金がかかるのか不安に感じる方もいるかもしれません。特に、譲渡所得税は金額が大きくなりやすいものの、一定の要件を満たせば控除を受けることもできます。
この記事では、土地売却時にかかる3つの税金「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」について、計算方法や納付のタイミングを分かりやすく解説します。譲渡所得税の負担を軽減できる特例や、税額のシミュレーションも紹介するので、ぜひスムーズな土地売却の参考にしてください。
土地売却時にかかる税金の種類

土地売却時にかかる税金は、主に「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」の3つです。
税金の種類 | 内容 |
|---|---|
譲渡所得税 | 売却による譲渡所得に対してかかる税金。所得税・住民税・復興特別所得税の総称。 |
印紙税 | 売買契約書に対してかかる税金。 |
登録免許税 | 土地に住宅ローンの抵当権が設定されている場合、その抵当権を抹消するための登記にかかる税金。 |
これらの税金は、それぞれ計算方法や納付するタイミングが異なります。特に譲渡所得税は、売却する土地の状況によって高額になる可能性もあるため、仕組みを正しく理解しておくと安心です。
土地売却でかかる税金①譲渡所得税
譲渡所得税は、土地などの不動産を売却した際の「譲渡所得」に対して課せられる税金です。譲渡所得税という名称の税金があるわけではなく、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つを合わせた総称です。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の課税対象となる「譲渡所得」は、土地の売却益そのものではありません。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 − (取得費用 + 譲渡費用)
取得費用: 土地の購入代金、購入時にかかった仲介手数料などの費用のこと。
譲渡費用: 売却時にかかった仲介手数料など、売るために直接かかった費用のこと。
上記の計算式で求めた譲渡所得に、所定の税率をかけて譲渡所得税を求めます。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得税の税率は、売却した土地の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。それぞれの税率は以下のとおりです。
区分 | 所有期間 | 税率(所得税+復興特別所得税+住民税) |
|---|---|---|
長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% (所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% (所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |
所有期間は、売却した年の1月1日時点を基準にカウントします。5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、売却のタイミングを判断する重要な基準になるでしょう。なお、譲渡所得税にはさまざまな特例が設けられており、適用できれば税額を大きく抑えることも可能です。
譲渡所得税を納付するタイミングと方法
譲渡所得税のうち、所得税と復興特別所得税は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日まで(年によって異なる場合あり)の間に、確定申告を行って納付します。
住民税は、確定申告の内容に基づいて税額が計算され、申告した年の5月以降にお住まいの区市町村から納税通知書が送られてきます。その通知書にしたがって、一括または年4回に分けて納付(普通徴収)するのが一般的です。
会社員や公務員の方で、確定申告の際に「給与から差引き(特別徴収)」を選択した場合は、その年の6月以降、毎月の給与から天引きされる形で納付します。
土地売却時に使える税金の特例
土地売却で利益が出た場合でも、その土地が自宅の敷地だったり、親から相続したものだったりする場合には、特例を利用できる可能性があります。これらの特例は自動的に適用されるわけではなく、確定申告で申請しなくてはならない点に注意が必要です。また、それぞれ細かな要件が定められているため、自分だけで判断せず、不動産会社や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
マイホームの土地を売却する際に使える特例2選
一定の要件を満たす自宅の敷地を売却する場合には、次の2つの特例が利用できる可能性があります。これらは併用することも可能です。
特例の名称 | 内容 | 主な適用要件 |
|---|---|---|
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度。 | ・自宅の家屋や敷地の売却であること。 ・住まなくなった日から3年が経過する年末までに売却すること。 ・売却した年の前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 |
10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、譲渡所得6,000万円以下の部分について税率が14.21%に低減される制度。 | ・自宅の家屋や敷地の売却であること。 ・売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること。 ・3,000万円特別控除以外の特例の適用を受けていないこと。 |
相続した土地を売却する際に使える特例2選
相続した土地を売却する場合にも、税金の負担を軽減できる特例が利用できます。代表的なものは次の2つです。
特例の名称 | 内容 | 主な適用要件 |
|---|---|---|
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 | 故人が一人暮らしをしていた家屋と敷地を相続し、売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度。 | ・相続開始直前まで故人が一人で居住していたこと。 ・1981年5月31日以前に建築された家屋であること。 ・相続開始日から3年が経過する年末までに売却すること。 ・売却代金が1億円以下であること。 |
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 | 相続した土地を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を土地の取得費用に加算できる制度。 | ・相続で取得した土地を売却すること。 ・相続で土地を取得した人に相続税が課税されていること。 ・相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること。 |
土地売却でかかる税金②印紙税

土地を売却するとき、買主との間で「不動産売買契約書」を取り交わします。この契約書に印紙を貼り付ける形で納めるのが印紙税です。
印紙税の計算方法
印紙税の金額は、売買契約書に記載された契約金額(売却価格)に応じて決まります。不動産の売買契約書については軽減措置が設けられており、2027年3月31日までに作成された契約書には、下表の「軽減税率」が適用されます。
契約金額(一部抜粋) | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
印紙税を納付するタイミングと方法
印紙税は、税額に相当する収入印紙を売買契約書に貼り付けて、消印(割印)をすることで納付します。収入印紙は、郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。売買契約書は、当事者双方の保管用に2通作成するのが一般的なため、売主と買主がそれぞれ1通ずつ印紙税を負担するのが通例です。
土地売却でかかる税金③登録免許税
売却する土地の住宅ローンを返済中の場合、土地には金融機関による抵当権が設定されています。売却するには、買主に引き渡すまでに、抵当権を抹消しなくてはなりません。この「抵当権抹消登記」を行う際にかかる税金が登録免許税です。抵当権が残ったままでは、買主は安心して土地を購入できません。そのため、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、売主が負担するのが基本です。
ちなみに、土地の所有権を買主に移す「所有権移転登記」にも登録免許税がかかりますが、こちらは買主が負担するケースがほとんどです。
登録免許税の計算方法
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。戸建てで住宅ローンを借りる場合、土地と建物の両方に抵当権が設定されているケースが大半でしょう。この場合、土地と建物それぞれで不動産1つとカウントされるため、納付する登録免許税は2,000円となります。
登録免許税を納付するタイミングと方法
登録免許税は、抵当権抹消登記を申請するタイミングで納付します。登記の手続きには専門知識が求められるため、司法書士に依頼するケースが一般的です。その場合、登録免許税は司法書士への報酬と一緒に支払い、司法書士が代理で納付してくれます。
土地売却でかかる税金のシミュレーション

それでは、実際に土地を売却した場合、税金はいくらになるのでしょうか。具体的な条件を設定してシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーションの条件】
土地の売却価格:3,000万円
譲渡費用(売却にかかった費用):150万円
土地の取得費(購入価格+購入費用):1,650万円(購入価格1,500万円+購入費用150万円)
売却した年の1月1日時点での所有期間:20年(長期譲渡所得)
【ケース1:自宅の土地ではない場合】
1. 譲渡所得の計算
3,000万円(売却価格) − (1,650万円(取得費) + 150万円(譲渡費用)) = 1,200万円
2. 譲渡所得税の計算
所有期間が20年なので、長期譲渡所得の税率20.315%を適用します。 1,200万円(譲渡所得) × 20.315% = 243万7,800円
3. 印紙税の計算
売買契約金額が3,000万円なので、1万円(軽減税率)となります。
合計税額:243万7,800円 + 1万円 = 244万7,800円
【ケース2:自宅の土地の売却で特例を適用する場合】
この土地が自宅の敷地(住宅ローン完済済み)で「3,000万円の特別控除」を適用できる場合、次のように計算できます。
1. 譲渡所得の計算
まず、ケース1と同様に譲渡所得を計算します。
3,000万円 − (1,650万円 + 150万円) = 1,200万円
2. 3,000万円の特別控除を適用
次に、譲渡所得から3,000万円を控除します。
1,200万円(譲渡所得) − 3,000万円 = −1,800万円
譲渡所得が0円を下回ったため、課税譲渡所得は0円となります。
3. 譲渡所得税の計算
課税譲渡所得が0円なので、譲渡所得税は0円です。
4. 印紙税の計算
ケース1と同様に1万円です。
合計税額:0円 + 1万円 = 1万円
このように、特例を適用できるかどうかで、税金の負担額は大きく変わるのです。
まとめ
土地の売却には、譲渡所得税、印紙税、登録免許税という3つの税金がかかります。印紙税は必ずかかるものですが、譲渡所得税や登録免許税がかかるかどうかは状況次第です。特に、譲渡所得税はまとまった金額になる場合もありますが、3,000万円の特別控除など、負担を大幅に軽減できる特例も用意されています。
税金の計算や手続きは複雑ですが、あらかじめ必要な知識を身につけておくことが大切です。もし不安な点や分からないことがあれば、不動産会社や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。